個性が生きる、チームで広がる。厚真町の林業は、もっともっと面白くなる。(後編)
2025年1月28日

前編では3人の林業家たちの道のりと、厚真町の林業の未来について熱く語ってもらいました<厚真町の林業が熱い。森人たちの挑戦の軌跡と、描く林業の未来>。後編は3人による対談。同じフィールドで活動する3人だからこそ見えるお互いの強み、個性を掛け合わせチームで取り組む活動の可能性についても語ってもらいました。
前編はこちら⇒https://atsuma-note.jp/atsuma-ringyou-mirai/
産業の活性には、外からの刺激も、地元の理解もどちらも必要
―実は、2020年にも3人で対談をしていますよね<【協力隊×林業で起業!】「厚真町は自由度があって挑戦しやすいまち」。林業などに挑戦して共にまちをつくる人、待っています>(https://atsuma-note.jp/atsuma_ringyou2020/)4年経った今、それぞれの成長と、お互いの事業や活動をどのように見ていますか?
西埜:丹羽さんの会社には、若者たちがどんどん集まっているイメージがあるかな。それから、イベントに積極的に出展したり、丹羽林業グッズを作ったり林業を楽しんでいるように見えますね。
中川:確かにそうだね。奥さんのパワーがすごいし、頑張っているのが伝わってくる。
丹羽:企画を考えているのが妻なので、彼女がいないと成り立たないですね(笑)積極的に表に出るようになったのは、4年前と比べると確かに変わったことの一つです。妻の他にグッズのデザインなどを一生懸命やってくれている社員がいることも大きいと思います。

中川:これまでの林業会社には見られない動きだし、すごいことだと思いますよ。林業の業界の人たちって、休日まで関係者と集まったり、顔を合わせることってほぼなかったからね。どちらかというと、集まりたくないっていう(笑)
西埜:社員・スタッフをまとめあげる力がすごい。みんな楽しそうにやってるし。
丹羽:イベントを始めたのは、山にあるものを目に見える形で伝えられないか…と思ったのが一つのきっかけだったんですよ。最初は林業現場でよく使う手拭いをグッズ化したんだけど、それだけじゃ物足りないのでワークショップをやってみようと。実際にスタートしてみたら物珍しがられて、いろいろなイベントに呼ばれるようになりまして。今はグッズも少しずつ増えて、チェンソーの受口を模したキーホルダーを作ったりしながら、林業や樹木の魅力を少しでも知ってもらう入り口づくりをしています。
中川:西埜さんは馬が増えたね。馬耕を始めたり、ハスカップ栽培の他にもブドウも植え始めたり事業の幅が広がっている。薪が万里の長城みたいになってるし、敷地内がどんどんテーマパークみたいになっているのも面白い(笑)それから、やっぱりファンがすごいよね。
丹羽:西埜さん自身がとても楽しそうに仕事をしているし、訪れる人たちも楽しそう。町内外から、多種多様な人が遊びに来ていますよね。
西埜:馬の効果だと思うよ(笑)
中川・丹羽:いやいやいや。

西埜:事業を始めた当初は馬が1〜2頭だったので、4頭になって倍の規模になりましたね。中川さんも、製材所を作って着実に前に進んでいるよね。製材所を建てるって、とてつもない覚悟が必要だったと思う。ビジョンを持って実行するって相当難しいことで、それを厚真町に移住して5年かけて実現したわけじゃないですか。最初からその姿を見てきただけに、すごく感慨深いです。製材所設立はイメージ通りに進んでいったのか、それとも想定より早く実現したの?
中川:最初は製材所を建てるにも、一体いくらかかるものなのか想像もつかなかったんですよ。前進できたのは、補助金の申請が通ったことが大きくて。商工会の方が優秀で、活用できる支援について教えてくれたり、申請を手伝ってくれたり。本来であれば自分のように小さな事業者が資金を調達するってなかなか厳しいけれど、補助金の審査が通ったことで銀行からも資金を借り入れできたんだよね。西埜さんも、そうじゃなかった?
西埜:そうそう。厚真町に来て事業をスタートした頃は、大変お世話になりました。
中川:商工会の方がいなかったら、僕たちの今はないよね(笑)

―厚真町の林業は町外の人たちから「面白そうなことをやっている」と注目を集めていますが、評価をどのように受け止めていますか?
丹羽:中川さんや西埜さんをはじめ、町外から移住していろいろな事業を行っている人たちの力や影響がすごいと思っていて。皆さんが林業を盛り上げてくれるから厚真の森や林業が総じて評価されていて、自分はそれに相乗りさせてもらっているような…。
中川:そんなことはないでしょう!
西埜:そうそう。僕たちにとっては、丹羽林業のように地元企業でありながらも移住者を受け入れてくれる会社があることに安心感を持てている。丹羽さん自身も森林の仕事ガイダンス(新たな林業の担い手の確保・育成を目的に、森林・林業に関心を持つ方を対象に実施する説明・相談会)のような場所に積極的に参加して魅力を発信しているから、若い人たちが集まってくるんじゃないかな。地元企業と個人林業家・移住者がこんなに良い関係性でいられるのって、当たり前のことじゃないんだよね。馬搬でトラブルが発生した時には、重機を快く貸してくれたり。本当にありがたいと思っています。
中川:外からの刺激も地元企業の理解も、どちらも必要ってことだよね。うちの製材所にも「こんな丸太が欲しい」って言ったら、良いのを見つけて卸してくれるし。
丹羽:中川さんのニーズに見合った木が、結構タイミングよく現れるから(笑)
中川:うちのような規模の製材所はたくさんの木材を必要とするわけではないから、一般的な林業会社は相手にしてくれない可能性が高いんですよ。本来であれば経営的にもコストパフォーマンス的にも、大口の安定した取引先に卸したいはずだけど、真面目に相手をしてくれている。
西埜:この関係性って、すごい価値だよね。

それぞれの個性をクロスさせ、林業をさらに魅力あるものに
―前編では、それぞれが抱えている状況や課題についても伺いました。4年前の皆さんだったら言えなかったことも、経験値を積んだ今なら言えること・できることがあるかもしれません。西埜さんは馬にとってちょうど良い仕事をコンスタントに得ていくことが課題でしたね。
丹羽:それについては、西埜さんとずっとやってみたかったことがあるんですよ。大きな重機では入れないような山に馬搬で入ってもらって、傷つけずに木を搬出してもらう。そこから先は、丹羽林業の稼働力を生かして運んでいく。お互いのメリットを生かして、デメリットを補完し合うことができるんじゃないかと思っているんですよね。
西埜:それは嬉しい!今は全てを自己完結してやろうとしているから、馬搬では厳しい条件・規模感でも引き受けているところもあるので。丹羽林業とタッグを組むことで、広がる現場もたくさんあると思います。
―丹羽さんの課題は、個人として取り組みたいこと・会社で取り組むべきことの狭間にいるとのことでした。
丹羽:厚真町の植生・広葉樹を生かすことができれば、木の価値を高めることにも繋がります。そうすれば針葉樹は必要な量を植えて、必要な量を切るだけですむ。特に林業は人手不足が進んでいるから、作業にかかる労力を減らすこともできるんじゃないかと。反面、会社としては機械を遊ばせずに、効率よく事業を回してくことも必要ですからね。
中川:厚真町には林業会社が丹羽林業の一社しかないから、針葉樹もしっかりやっていかないとならないもんね。 会社が大きくなれば、どちらも実現できるのかな。
西埜:20人体制くらいになれば、両立の可能性はあるよね。5人は広葉樹担当、15人は針葉樹担当みたいにして。
丹羽:会社の規模を大きくするには、技術者を育てることと、その林業技術を教えられる人を育てることも必要なんですよね。
西埜:丹羽さんが所属している胆振林業青年部では、Woodsman Workshop LLCの水野さんによる伐倒技術講習会を町内で開催したり、研鑽を積んでいるよね。それも自分の会社の社員だけでなく、地域の人たちにも講習を受けられるように間口を広げていて。
―広葉樹の需要を増やすには、クライアント(山主や企業など)や一般ユーザー(木材購入者)に対して取り組みの価値を知ってもらう必要があるかもしれません。PR・情報発信の面では皆さんの個性や力を活かす可能性はありそうですか?
丹羽:そういった意味では、中川さんのミックスフローリングは広葉樹の魅力を伝えられる良い商品ですよね。
中川:そうですね。ただ丹羽さんの仕事はクライアント(山主)ありきだから、ユーザーから「こんな木が欲しい」とオーダーがあっても自由に木を切り出してもらえるとは限らない難しさが残っているよね。クライアントと林業会社の関係性(受発注の自由度)を構築すること自体が高いハードルとしてある…。可能性がありそうなのは、町有林かな?
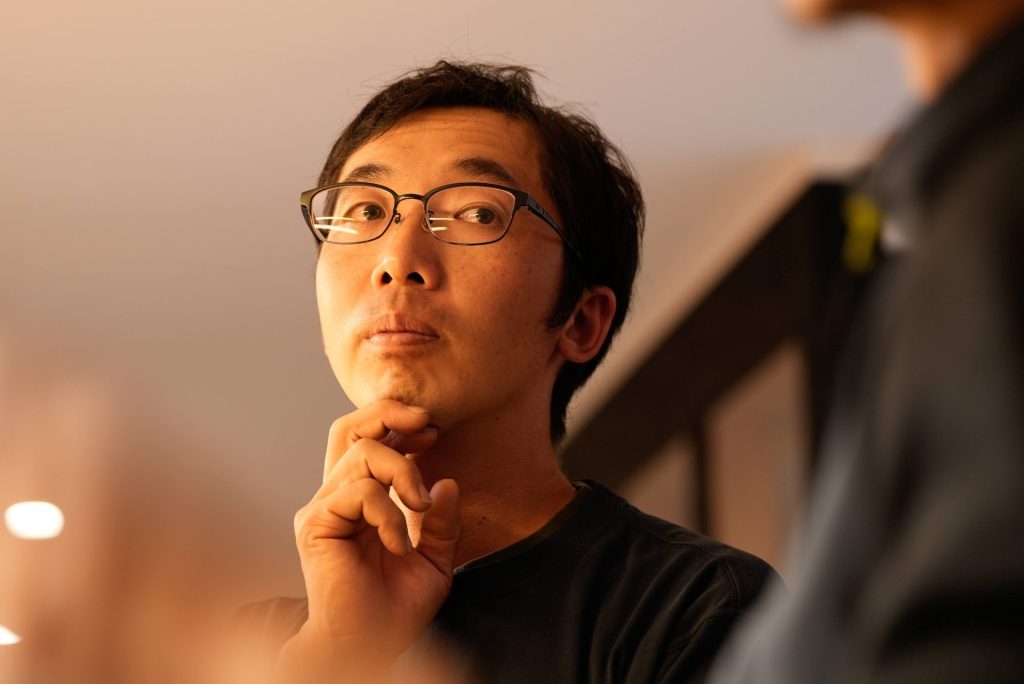
丹羽:働きかけによるかもしれません。町有林は、町民の財産だから町民からの要望があれば可能性はありますね。現段階では、軽舞水利用組合の所有している山林(地域の有志がゴルフ場跡地を買い取った土地)をうまく活用できないかと思っています。
中川:自分も、本当はもっともっと西埜さん・丹羽さんともコラボした商品を開発できたらいいなと思っていて。森に足を運んで、彼らがやっている仕事を生で見てもらう、そして製材所に来てもらう。その流れがあって初めて、厚真町の林業者たちが手がけた物を欲しいと思ってくれるお客さんが現れたり、広葉樹の森づくりの価値を理解してもらえるんじゃないかと。気軽に続けられるのは、自分たちの仕事を見てもらうオープンデーかな。手前味噌だけど、自分が開催した「製材所開き」は良かったと思う。丹羽さんが木を伐採して、西埜さんが馬で引っ張って、自分が製材してっていう流れを見てもらえた。

丹羽:同感です!町中でやるイベントと違って、なかなか地元の人が参加しない類のイベントにも関わらず、たくさんの人が集まっていたのがすごいなぁと思いました。
丹羽:地元の食堂のおじさんとかも来てくれていたもんね。
中川:そうそう。これまでお世話になった人、地元のおじいちゃんおばあちゃんも来てくれてね。近所の人が炊き出しを手伝ってくれたりもしたんだよ。ちょうど妻がインフルエンザで寝込んでしまって、開催ギリギリのお願いにも関わらず助けてくれた。
丹羽:それは感動しますね!
西埜:本当にそう思う。実は前から考えていたのが、大黒柱ツアー。新築の家を建てるお客さんと一緒に森で木を選ぶところから始めて、伐採して、馬で運んで製材する。同じようなスタイルで、テーブルとか家に置ける一生物の製品を作るっていうのも面白いんじゃないかな。
中川:そういうイベントとかワークショップ、ツアーなんかを続けていたら、また何か面白いことが起こるかもしれないね。

次世代に残る森づくりと林業を、今から続けていく
―5年後、10年後、さらにその先の厚真の森はどうなっていてほしいですか?どんな世界を見てみたいと思いますか?
中川:やっぱり100年単位の広葉樹が、常に、どこかしらに生えている環境がほしい。製材していて分かるのは、年齢を重ねた木は質がいいということ。太く育つにつれて枯れた枝の跡(死節)が巻き込まれていき、見た目も質も良い木材に仕上げられる。魚でいうと、魚体が大きいと脂が乗って肉厚になるじゃないですか。マグロのトロの部位が増えていく感じ(笑)魚と木って似ていて、種類が多様でそれぞれ味も色も身の性質も違う。養殖した魚はいつでも買えるけれど、天然物はいつ手に入るかわからないし、旬もある。それが丸太とそっくり。
西埜:魚屋のように丸太を売りたいんだね(笑)
中川:(笑)広葉樹に話を戻すと、脂が乗り切る前に切りすぎているんだなと思う。そういう風潮も少しずつ変わってきてはいて、今はどちらかというと将来競争では勝てない広葉樹を間伐している段階。間伐して出てきた丸太は、そこまで質が良くなくても今はそれで良くて。あと30年したら太くて質の良い木ができるから、若い木も製材でなんとか質を引き上げながら、年齢を重ねた太い木も回ってくる状態にする。結果的に太い木を切るための技術者も育つし、山の環境が良くなることで栄養分が農地や海にも運ばれて、他の一次産業にとってもプラスの環境になっていくと思います。それが、一部だけでなく広範囲の山に広がっていったらすごくいいよね。
丹羽:僕は、子どもたちが大人になった時、厚真町に戻って林業に携わっている姿を見られたらいいなと思っています。厚真町の小学生は、授業で「ふるさと教育」*1の一部として一次産業に関わるプログラムに取り組んでいるんですが、林業もその一つに組み込まれているんですね。現場に行ったり、調べ物をしたり、体験をしたり。実は最近、ふるさと教育を経験した子どもの中から、将来の夢が「林業をやりたい」って子が現れたんですよ!
*1「ふるさと教育」・・・小中学校9年間を通してふるさと「厚真町」について深く学ぶ取り組み
中川:それはすごい。
丹羽:少し前まではありえないことだったので、嬉しくなりました。林業に対して良いイメージを持ってくれるようになったことの表れだと思うので、そこを伸ばしていきたい。こういった取り組みが、巡り巡って自分たちにも良い影響を与えてくれると思っています。
中川:次世代の林業に関わってくれる人を増やすことができないと、100年の森はできないからね。
西埜:そうだよね。自分が見たいのは、イベントなど特別な時だけでなく、当たり前のように馬搬が町の風景の中にあることかな。ヨーロッパで馬搬を見て感動したように、ダイナミックな林業風景が見られる時が来たらいいなと思う。「こんな林業もあるんだ」「厚真に来たら見られるんだ」みたいに感じてもらえたら。林業が「楽しそうな仕事」に向かっているといいですね。イメージをしっかりと持っていれば、あとは自然とその方向に進んでいく気はしています。
中川:やりたいことからブレないこと。それから、チームとして協力・挑戦しやすい空気感を作っていくことは大事だよね。森づくりも、広葉樹の価値を伝える活動も、皆でやり続けていきましょう!

樹木の多様性が豊かな森を形成していくように、それぞれの個性が集まることで厚真町の森や林業が豊かになっていく。一歩ずつ、しかし着実に、厚真町の森人たちは目指す未来に向かって進んでいます。これからもっともっと面白くなる厚真町の森で、あなたもチャレンジしてみませんか?
ローカルベンチャースクールについて詳細はこちらを参照ください。
厚真町 ローカルベンチャースクール https://atsuma-note.jp/lvs/
2024年度の募集は締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。
2025年度に向けてローカルベンチャースクールに関するお問い合わせは随時受付中です。また、厚真町の森に関わりたい方は是非一度、お気軽にお問い合わせください。
前編はこちら⇒https://atsuma-note.jp/atsuma-ringyou-mirai/
西埜将世さん(西埜馬搬)
中川貴之さん(木の種社)
丹羽智大さん(有限会社丹羽林業)
聞き手・文=長谷川みちる
写真=三戸史雄
